 |  | マラソンから持久走へ |  | | 2021/11/18 | 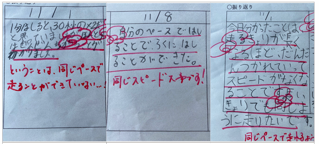 | 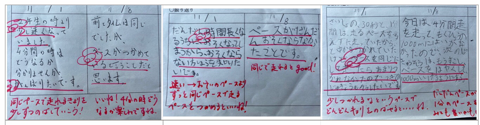 | | 秋があっという間に過ぎ,肌寒い季節がやってきました。朝,車に乗ってから暖房が効くまでが毎朝辛いですね。
学校行事の中で冬と言われるどんな行事を思いうかべますか?
一番はマラソン大会ではないかと思います。
私は体育が比較的得意な方だったので,マラソン大会は嫌いではありませんでした。むしろ走って良い順位を取るのが楽しかったと思いだされます。
では学生の頃,周りのみんなはどのように感じていたのかを振り返ってみると,「長い距離を走るのが辛い」や「順位が低いのを見られるのが恥ずかしい」という声もあったことを微かに記憶しています。
そこで,今更ながら長距離走というものを検討してみようと感じ,本校の行い方を変更するに至りました。どういう背景で変更し,どのような方法で行っていくのか,もし今行っているマラソン大会を変えたいと感じている方のお力になれたらと思います。
まず,本校で昨年度まで行っていたのは「決められた距離をどれだけ速く走れるかを競うマラソン大会方式」でした。いわゆるマラソン大会と呼ばれるものです。
それの何がダメなのか?と思われる方もいらっしゃると思いますので,私が考える課題をお示ししようと思います。
少し話は逸れますが,私が学生生活を過ごした鹿児島では,「指宿菜の花マラソン」や「鹿児島マラソン」などが開催されていました。ここ山口県でも有名なものであれば「下関海峡マラソン」があると思います。
現在はコロナ禍で,中止をせざるを得ないものもあると思いますが,コロナ禍以前にはたくさんの人が参加するスポーツイベントであったと思います。
この姿は,まさに「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現している」姿だと感じます。
ここで一つ疑問に感じたことがあります。こういったマラソン大会に参加している方々は,全員記録の向上を目指したり,順位を競うために参加しているのか?ということです。
もちろんそういった方もおられると思います。しかし,たくさんの方が,「マラソンを楽しもう」と思って参加されているのではないかと感じました。
例えば,ご当地のものが途中で食べられるから参加しようや,走るのが気持ちよいから参加しようや,友達としゃべりながら走ってみようなどのように,競争や記録の向上の観点を抜いて参加している方も多いのではないかと感じます。
では,小学校段階でこういった姿を実現するためにマラソンの学習をして,マラソン大会を行っているかと言われると,はいとは言い難いように思います。
ここがマラソン大会の課題と感じているところですが。この学習を行うことによって,「走ることが楽しい」「走ることが気持ち良い」という目指す姿の反対に感じる子どもが多いように思うからです。
これは,上記しました「長い距離を走るのが辛い」「順位が低いのを見られるのが嫌だ」といった感想が,マラソンや長距離走嫌いを生み出す要因になっていると感じます。
もちろんこういったことは,私が今初めて発見したわけではなく,先行研究も多く行われています。
あるテレビ番組で,日本の教育を視察しにきた外国の方々が,マラソン大会を見てがっかりしたと感想をもっていたこともありました。
では,指導要領はどうなっているのか?と思い。指導要領を開いてみますと,そもそもマラソンというものは小学校の指導要領には示されておりません。中学校では,陸上競技の中に「長距離走」というものが出てきます。しかし,小学校で近しいものを見つけるとするならば,体つくり運動領域に「持久走」という文言があります。それぞれ見てみると
低学年…体を移動する遊びにおいて,一定の速さでのかけ足(2〜3分)を通して,体を移動する動きを身に付けることができるようにする。
中学年…体を移動する運動において,一定の速さのかけ足(3〜4分)を通して,体を移動する動きを身に付けることができるようにする。
高学年…無理のない速さで5〜6分程度の持久走を通して,動きを持続する能力を高めることができるようにする。
というふうに書かれています。
機能的特性から考えると,従来のマラソン大会方式でいくと,競争して勝敗を競い合う楽しさや,記録に挑戦し,達成できた楽しさを味わうことが目的となっているように感じます。
こういった背景を鑑みて,体育部,本校で検討し,決められた距離をどれだけ速く走れるかを競うマラソン大会方式から,決められた時間でどれだけの距離を走れたかを記録する持久走記録大会に変更しました。
それでは,変更した行い方をお示ししたいと思います。
単元名は「ピッタリペース走」としました。
これは,山本貞美先生の実践である「折り返し持久走」をアレンジさせていただいたものです。
まず,簡単に行い方を説明します。
最初に30秒間で走れる距離を測定します。そこから1分間で走れる目標距離を設定し,1分間走を行います。30秒間と1分間だと,ペースを維持して走ることができるので,目標は概ね達成できます。では,その1分間走ることができた距離から4分間走の目標を設定します。
子ども達が設定した目標距離は700m〜1200mくらいで様々でした。4分間で1200mとなると,かなり速いと思います。そして4分間走を行ってみると,目標距離には到底たどり着けませんでした。
そこで,「なぜ,しっかり計算したのに目標距離に届かなっかたのか」と問いました。すると「1分間と4分間では,走る距離が違うから」や「最初は良いペースで走れていたんだけど,途中から遅くなっていたから」などの気付きが出てきました。
なので,「同じペースで走るためにはどうすればよいだろう」と目標を共有しました。
次時からはいよいよ「ピッタリペース走」を始めました。「ピッタリペース走」がどのようなものかを説明します。
1周200mのトラックにスタート位置を二つ設置します。それぞれのコーンから10m間隔でコーンを置き,自分の目標のコーンを決めます。
4分間終了時に,自分の目標のコーンから隣のコーン以内であれば2点,目標コーンから隣と二つ隣のコーンの間であれば1点,それ以外の場所であれば0点という風にゲーム要素を取り入れて行いました。
しかし,初めての「ピッタリペース走」では,得点を取れた子どもは数人でした。子どもはどうすれば良いかを試行錯誤して走っていましたが,自分だけではなかなか難しいようでした。
この学習過程でグループ活動を取り入れると,同じペースで走るためにはという視点が焦点化されやすいように感じました。
従来のマラソン大会方式でグループ活動を行うと,陸上運動領域で取り扱うような記録の伸びを得点化する方法になると思います。しかし,記録が伸びないと視点がそれるといったこともしばしば見られます。もちろん友達との関わり合いや,教師の働きかけによって変容すると思いますので,この方法を否定してるわけではありません。
まだ本格的にグループ活動を始めていませんので,今後この単元でもグループ活動上で上手くいかないことがあると思います。またいろいろな手立てが考えられたらと思います。
個人の振り返りにはなりますが,集めたものを載せておきます。ペースや,体を動かすことに着目している子がたくさん見られました。
見辛くなっているところもありますので,こちらにも載せておきます。
・「1分走ると30秒の×2だと思っていましたが,ほんとうはぜんぜんちがうことがわかりました」
・「自分のペースで走ることで,楽に走ることができた。」
・「今日分かったことは,走る距離が長くなるほど,だんだんつかれていってスピードがなくなることです。長い距離でも同じように走りたいです。
・自分のペースで走ってみたいけど,同じいきおいでは走れなかったから,次は同じいきおいで走ろうと思います。
・自分のペースで走れたから,すごく走れた。
・ほかの人とは,差が大幅にあったけど,頑張ったから良いと思います。
・800mいけたかと思ったけど,680mだったから,今度4分間でやったときはもっと速く走りたい。
・前と同じ距離でしたが,ペースがつかめたということだと思います。
・段々時間が長くなるうちに,遅くなってしまうから,遅くならない方法を知りたいです。
・ペースがだんだん遅くなりませんでした。
・最初の30秒と1分はペースを考えずに走っていたから,途中から疲れていたけど,ペースを同じにして走ったらあまり疲れなかったので,次の授業もそうしたいです。
・今日は4分間走をして,目標の1000mにはいかなかったので,次の授業では,もう少しペースを速くして1000mいけるようにしたいです。
(一部漢字変換,聴き取りにより記述内容との違いあり)
まだまだ変更したばかりで,至らぬ点が多いと思います。何かお気付きなどありましたらご教授いただければと思います。
また,マラソン大会を変更したいけど,どうしようと思っている先生がいらっしゃれば一緒に考えさせてください。
冬の持久走学習を有意義なものにできるように更に検討していきたいと考えております。
長くなりましたが,最後まで読んでいただきありがとうございました。 | |  |



